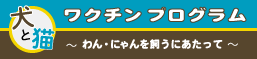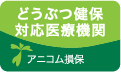お知らせ一覧
「神奈川県獣医師会学術症例報告会」で発表しました! /2005年03月25日号
- 2006年3月9日 神奈川県獣医師会学術症例報告会
- マーブル動物病院からの演題
- 1.内科療法で管理している犬インスリノーマの1例
- 難波信一1) 日比佐知子1) 大沼和気子1) 小笠原静香1) 桑原岳1) 伊藤典子1)マーブル動物病院1)・神奈川県藤沢市
- 2.高エストロゲン症により貧血を呈したと考えられる1例
- 日比佐知子1) 大沼和気子1) 小笠原静香1) 伊藤典子1) 桑原岳1) 難波信一1)マーブル動物病院1)・神奈川県藤沢市
- 3.猫の眼瞼結膜に発生したリンパ腫の一例
- 大沼 和気子1)、日比 佐和子1)、小笠原 静香1)、伊藤 典子1)、桑原 岳1)、難波 信一1)
(1)マーブル動物病院:神奈川県藤沢市
- 4.マダニ寄生が認められた犬21頭におけるボレリアならびにエールリッヒアの抗体調査
- 小笠原 静香1)、日比 佐和子1)、大沼 和気子1)、伊藤 典子1)、桑原 岳1)、難波 信一1)
(1)マーブル動物病院:神奈川県藤沢市)
- 5.脊髄変性症が疑われる一例
- 桑原 岳1) 日比 佐知子1) 大沼 和気子1) 伊藤 典子1) 小笠原 静香1) 難波 信一1)
マーブル動物病院1)・神奈川県藤沢市
- 6.骨に発生した犬の血管肉腫の一例
- 伊藤典子1)、日比佐知子1)、大沼和気子1)、小笠原静香1)、桑原岳1)、難波信一1)、市村豊2)
マーブル動物病院1)、市村動物病院2) 神奈川県藤沢市
1.内科療法で管理している犬インスリノーマの1例
○難波信一1) 日比佐知子1) 大沼和気子1) 小笠原静香1) 桑原岳1) 伊藤典子1)マーブル動物病院1) ・神奈川県藤沢市
I.はじめに
インスリノーマは、犬ではまれ、猫では極めてまれな腫瘍である。中年齢から老齢で発生することが多く、雌雄による性差はないとされている。ジャーマン・シェパード、ボクサー、スタンダード・プードル、アイリッシュ・セッター、コリー、フォックス・テリアなどが好発犬種とされており、高率に転移することから予後不良と言われている。今回、我々は膵臓に散在性のインスリノーマが発生し、現在までプレドニゾンとβブロッカーで良好に維持できている症例に遭遇したので、その概要を報告する。
II.症例
シーズー、不妊手術済みメス、13歳7ヶ月、体重7.9kg、BCS 5/9。ワクチン、フィラリア等の予防は完全に行われていた。「2-3週間前から足がふらついていたが、今日は特にひどい。尿もポタポタ漏らしてしまう。」という稟告で来院。身体一般検査では、体温38.3度、心拍数140bpm、呼吸数24回/分。後躯にふらつきが認められ、前肢の固有知覚反応は、両肢とも弱く、左よりも右の方が弱かった。
Ⅲ.治療および経過
来院時(第1病日)に血液検査、血液生化学スクリーニング検査、尿検査、X線検査を行い、血液検査異常として、低血糖(21mg/dl)が認められた。尿検査では、特に異常は認められなかった。腹部単純X線検査では、幽門尾側と横行結腸の間隔が広がっていたこと、腸管内のガス貯留が認められたこと、卵巣子宮摘出時に使用したと思われるヘモクリップが腹腔内に認められた以外には異常が認められなかった。追加検査として、血中コルチゾール濃度の測定と血中インスリン濃度の測定を行ったところ、両者とも上昇を示していた。また、来院時の低血糖に対して 5% ブドウ糖液の静脈内投与を開始すると、臨床症状は劇的に改善したが、中止すると24時間以内に再発した。以上の所見からWhippleの三徴(空腹時の意識消失発作、発作時血糖が 50 mg/dl 以下、ブドウ糖投与による症状改善)を満たしていると考え、インスリノーマと仮診断した。第4病日にCT検査を行い、そのまま開腹手術を行った。肉眼所見として、膵臓は全体にわたって硬化しており、付属の血管群も硬化していた。また、粟粒大の結節が膵臓全体にわたって散在性に認められたため、病理組織検査に提出する材料を採取するに留めた。尚、開腹時、隣接した組織に異常は認められなかった。病理組織の結果を含め、本症例をインスリノーマと確定診断した。
第10病日、病態と治療法について飼い主に説明して同意が得られ、聴診、胸部X線検査ならびに心エコー検査で異常が認められなかったため、プレドニゾン(1mg/kg sid po)にβブロッカー(プロプラノロール:1mg/kg bid po)を併用して治療を開始した。 治療開始直後には、血糖値が不安定であったものの、現在180日以上経過しているが、空腹時血糖は 100-180mg/dl、フルクトサミンは 300μmol/L 前後で推移しており、全身状態も極めて良好である。
Ⅳ.考察
犬のインスリノーマに対する治療法としては、孤立性腫瘍であれば、手術による摘出が推奨されている。しかしながら、本症例のような散在性のインスリノーマの場合、内科治療が適応と考えられる。現在使用されている薬剤には、ストレプトゾシン、アロキソン、ジアゾキシド、プレドニゾン、βブロッカーが挙げられる。ストレプトゾシンは副作用、ジアゾキシド、アロキソンについては国内で入手不可能なことからプレドニゾンとβブロッカーを使用した。肝臓の糖新生を誘発し、末梢の糖消費を低下させることによって血糖値を上昇させる作用があるプレドニゾンに、主に膵臓β細胞のレベルでインスリンの放出をブロックし、血中グルコース濃度を増加させる効果があるβブロッカーを併用するのが、安全、安価で効果的であると考えられる。
2.高エストロゲン症により貧血を呈したと考えられる1例
○日比佐知子1) 大沼和気子1) 小笠原静香1) 伊藤典子1) 桑原岳1) 難波信一1)マーブル動物病院1)
・神奈川県藤沢市
Ⅰ.はじめに
エストロゲンは主に卵巣と胎盤から分泌され、過剰に分泌されることにより、非再生性貧血、血小板減少症、骨髄の過形成または低形成、 毛包の萎縮による対称性脱毛引き起こすことが知られている。 今回、高エストロゲン症により貧血を呈した症例に遭遇したのでその概要を報告する。
Ⅱ.症例
雌のトイ・プードル、12歳齢、ワクチン・フィラリア等の予防は完全に行われていた。 11ヶ月前に股関節脱臼のため右骨頭切除術を行った。 3年前より発情に気づかなくなっていたとのことだった。 半年前に血漿中エストラジオールおよびプロゲステロン濃度の測定を行い卵巣機能不全の存在を確認し、卵巣子宮摘出術を勧めていた。 1ヶ月前に陰部を舐めていて、陰部が腫脹しているとのことで来院したが子宮に液体貯留はなく身体検査に問題なかったため経過観察と1週間後の再診を予定した。 主訴は2日前から食欲・元気がないということで、来院時の身体一般検査では体温37.7度、心拍数96回/分、呼吸数48回/分であった。 体重は5.36kg、ボディコンディションスコア3/6、1ヶ月前よりも200g減少していた。可視粘膜の蒼白が認められた。 出血や皮膚の紫斑は認めらなかった。
Ⅲ.治療および経過
来院時(第1病日)に血液検査、X線検査を行った。 血液検査異常として、赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビンの減少が認められた。 黄疸および溶血は認められなかった。CRPが上昇していた。胸腹部単純X線検査において異常は認められなかった。 赤血球指数から大球性低色素性貧血の再生性貧血に分類され血液塗抹では赤血球の大小不同および少量の多染性が観察された。 貧血の原因を鑑別する目的で追加検査を行った。卵巣の機能異常が存在したためエストロゲン過剰による骨髄抑制を考えて、 血漿中エストラジオールおよびプロゲステロン濃度の測定を行った。 また免疫介在性溶血性貧血を鑑別するために抗核抗体検査およびクームス試験を行った。 血中エストロゲン濃度は139.67pg/mLと著しく上昇し、血中プロゲステロン濃度も30.95ng/mLと高値で、貧血はエストロゲン過剰によるものと診断した。 しかしながら、免疫介在性溶血性貧血も否定できないためにプレドニゾロン2mg/kgで開始した。 翌日(第2病日)に卵巣子宮摘出術を行った。卵巣には卵胞と黄体が同時に存在した。子宮は部分的に子宮体部に肥厚した部分を認めた。 第2病日より食欲・元気は改善して第3病日より貧血は少しずつ改善された。 プレドニゾロンは漸減し、終了して1ヶ月後の第49病日にPCVは正常範囲になった。 抗核抗体検査は陰性、クームス試験は37℃および4℃ともに128倍で陽性であった。
Ⅳ.考察
エストロゲンによる骨髄抑制のメカニズムはまだはっきりと解明されていないが、骨髄抑制の感受性は動物種で異なり、 犬では比較的感受性が高く、個体差があることが知られている。エストロゲンによる骨髄抑制の場合、貧血は非再生性に分類されるが、 今回再生性に分類されたのは骨髄の抑制が完全ではなかったからと考える。 現在、貧血は改善しているがクームス試験が陽性であったために、経過観察が必要であると考える。
3.猫の眼瞼結膜に発生したリンパ腫の一例
○大沼 和気子1)、日比 佐和子1)、小笠原 静香1)、伊藤 典子1)、桑原 岳1)、難波 信一1)、
(1)マーブル動物病院:神奈川県藤沢市)
Ⅰ.はじめに
犬猫において眼は一般的な腫瘍発生部位ではなく、また眼疾患の一般的な原因でもないといわれている。 猫の眼瞼結膜の腫瘍は発生が少なく、また、扁平上皮癌がその中でも発生が多く、リンパ腫の発生はあまり多くないとされている。 今回、眼球結膜の腫脹を主訴に来院し、眼球および、結膜の外科的摘出を行い、病理組織学的検査の結果リンパ腫と診断された症例に遭遇したのでその概要を報告する。
Ⅱ.症例
症例は18歳齢の雑種猫、避妊雌、体重2.00kg。完全に室内飼育で、混合ワクチン接種による定期的な予防を受けていた。 右眼の腫脹および鼻の蓄膿を主訴に来院した。初診時の身体検査所見では、鼻から膿性の鼻汁が認められ、 大きく膨れ上がった右眼の表面が潰瘍状になっていた。 血液学検査では白血球数の上昇(25630/μl)、貧血(PCV18%)および血小板数の軽度上昇(68.6×104/μl)が認められた。 血液生化学検査ではBUNの軽度上昇(36.9mg/dl)および血漿総タンパクの上昇(8.2g/dl)が認められた。 腹部および胸部レントゲン検査では特に異常所見は認められなかった。 食欲不振、および元気消失が見られたため全身状態の改善を図り、入院治療後7日目に全身麻酔下で眼球のCT検査および外科的摘出を行った。 CT検査において、眼球の前方に腫瘤が位置し、眼瞼結膜由来であることがわかった。 検査上では眼球と腫瘤の境界が比較的明瞭だったため、腫瘤のみの摘出を試みたが、腫瘤は角膜と癒着しており、眼球摘出術を実施した。 腫瘤の病理組織学的診断はリンパ腫であった。
Ⅲ.経過
術後の経過は比較的良好であったが、完全摘出が不可能であったため、術後一週間後に抜糸を行い、リンパ腫の抗癌剤プロトコールを考慮して、ビンクリスチンの3週間ごとの投与を開始した。 2回目の投与時の血液生化学検査で肝酵素の上昇(ALT311U/l、AST103U/l)が認められ、その後抗癌剤の副作用と思われる嘔吐が続いたが、 強肝剤および点滴により回復した。 3回目の投与時にはさらに肝酵素の上昇が認められ、一般状態の悪化も見られたため、抗癌剤の投与を中止し、 経過観察を行うこととなった。術後4カ月で来院した際には全身状態は比較的良好で再発も認められていなかった。
Ⅳ.考察
眼瞼の腫瘍では一般的に予後は組織型に由来するとされており、 外科的に早期手術を行った扁平上皮癌の場合では転移率が低いため比較的良好であるが、 マージンの切除が十分に行えなかった場合局所の再発が見られることが多い。 今回の症例では腫瘤の完全切除が不可能であったため、術後化学療法を開始したが、 抗癌剤の副作用により治療を断念せざるを得なかった。現在経過は良好であるが、今後も注意深い経過観察が必要と考えられる。
4.マダニ寄生が認められた犬21頭におけるボレリアならびにエールリッヒアの抗体調査
○小笠原 静香1)、日比 佐和子1)、大沼 和気子1)、伊藤 典子1)、桑原 岳1)、難波 信一1)、
(1)マーブル動物病院:神奈川県藤沢市)
Ⅰ.はじめに
ライム病は、野鼠や小鳥などを保菌動物とし、野生の マダニ(マダニ属マダニ)によって媒介される人獣共通の細菌(スピロヘータ)による感染症である。 犬に感染すると発熱、全身性の痙攣、起立不能や神経過敏などの症状を起こす。いっぽう、エールリッヒア症はヒトおよび動物の白血球に寄生するエールリッヒア(リケッチアの一種)による感染症である。 犬では元気・食欲減退、貧血などの症状を起こす。 今回、われわれはマダニ寄生が認められた、犬21頭における、ボレリアおよびエールリッヒアの抗体調査を行ったので報告する。
Ⅱ.疫学
欧米では現在でも年間数万人のライム病患者が発生し、さらにその報告数も年々増加していることから、社会的にも重大な問題となっている。 本邦では、1986年に初のライム病患者が報告されて以来、現在までに数百人の患者が、主に 本州中部以北(特に北海道および長野県)で報告されている。 欧米の現状と比較して本邦でのライム病患者報告数は少ないが、本邦においても野鼠やマダニの病原体保有率は欧米並みであることから、 潜在的にライム病が蔓延している可能性が高いと推測される。 感染症法施行後 の報告数としては、2002年に15例、2003年に5 例、2004年に4例となっている。
エールリッヒア症は世界的に分布していることが知られており、犬のほかにオジロシカやげっ歯類動物が感染源となる。 この病気は犬から犬への伝播にはイヌダニが関与していることが明らかになっているが、ヒトへの伝播に関与するダニの種類はまだ明らかではない。 犬は回復して健康に見えても4-5年は病原リケッチアを保有し続けることがある。
Ⅲ.方法
当院に来院している犬で、過去にマダニの寄生があった個体の静脈より採血を行い、 ELISA法を用いた簡易検査キット(IDEXX Canine SNAP 3Dx Test ; 日本未発売)を使用して判定した。
Ⅳ.結果および考察
今回検査を行った犬21頭において、ボレリア、エールリッヒア抗体は、すべての犬で陰性であった。アメリカにおける調査では、犬のボレリア、エールリッヒア抗体が陽性を示す地域は全域に渡っているが、今回の結果から、湘南地域におけるマダニの病原体保有率は欧米よりも低い可能性が示唆された。 なお、疫学調査としては検体数が少ないため傾向については言及できないが、臨床獣医師は両感染症に対する警戒を怠らないようにしなければならいと考えられる。
5.脊髄変性症が疑われる一例
○桑原 岳1) 日比 佐知子1) 大沼 和気子1) 伊藤 典子1) 小笠原 静香1) 難波 信一1)
マーブル動物病院1)・神奈川県藤沢市
Ⅰ.はじめに
脊髄変性症は5~14歳齢のジャーマンシェパードによく発生することから、ジャーマンシェパードの脊髄変性症(GSDM)とも言われる。 しかし他犬種で発生する脊髄変性症はデータが少ないため、GSDMと全く同じ病態かどうかは確認されていない。 また、MRIによる病変描出は不可能であり、除外診断が中心となるため確定診断が困難である。 今回、痛みを伴わない後肢の運動失調を主訴として来院し、神経学的検査および各種検査から脊髄疾患を疑って治療を開始したが、 症状の進行が止まらない一例について報告する。
Ⅱ.症例
症例は、ピレニアンマウンテンドッグ、雌、10歳齢、体重55.4kg。突然の後肢の運動失調、および不全麻痺を主訴として来院。 初診時神経学的検査所見:両側後肢の固有知覚低下、UMN兆候が見られた。背部痛は認められず自力排尿可能、浅部痛覚は存在した。 CBC、血液生化学検査所見:クレアチニンキナーゼの著明な上昇(2072U/L)が認められた。 ホルモン検査所見:fT4の軽度低下(4.21pmol/L)が見られた。 X線検査所見:側面像にてT4~T5、L2~L4に変形性脊椎症が認められた。 CT検査所見:X線検査にて確認された変形性脊椎症以外の異常所見は認められなかった。
Ⅲ.治療および経過
確定診断のつかないまま、神経学的検査からT3~L3に存在する脊髄病変と仮診断し、診断的治療を行った。 神経保護作用を目的としたメチルプレドニゾン15mg/kgの静脈内投与を行ったところ、翌日より起立可能になり自力歩行して退院した。 退院後はプレドニゾン(2mg/kg、BID)経口投与を二週間かけて漸減する予定であったが、 投与開始11日目(プレドニゾン1mg/kg、SIDにて投与5日目)再度起立不能になった。 再検査所見:神経学的所見は初診時とほぼ同じであったが、再発時には前肢起立時の震えがみられた。 血液検査所見:クレアチニンキナーゼの上昇は認められなかった(122U/L)。 プレドニゾンの投与量を初期値2mg/kgにもどし治療を開始したが、不全麻痺は両側前肢に進行し起立不能となり、現在に至る。
Ⅳ.考察
慢性進行性の歩様不全、麻痺が見られるが、背部痛が無いこと、排尿障害がないこと、CT検査にて圧迫物質が認められないことから、 椎間板ヘルニアは考えにくい。また、初診時X線検査にて股関節の形成不全が認められなかったこと、CT検査・神経学的検査から変性性腰仙部狭窄がみられないことより、 脊髄変性症が疑われる。ただ、CT検査で圧迫物資は確認されなかったものの、造影CT検査による圧迫部位の確認がなされていないことから、 2型椎間板ヘルニアが完全に否定された訳ではない。 また、初診時血液検査にてクレアチニンキナーゼの上昇が見られ、多発性筋炎などの筋疾患も考えられたが、 筋電図計を用いることができなかったために筋疾患の有無を除外しきれていない。 また、脊髄変性症ではCSF中のアセチルコリンエステラーゼの上昇が報告されている。 本症例を脊髄変性症と確定診断するには議論の余地が残るが、診断的治療の経過と長期的な予後については注意が必要と思われ、 慎重に経過を見守っていく予定である。
6.骨に発生した犬の血管肉腫の一例
○伊藤典子1)、日比佐知子1)、大沼和気子1)、小笠原静香1)、桑原岳1)、難波信一1)、市村豊2)
マーブル動物病院1)、市村動物病院2) 神奈川県藤沢市
Ⅰ.はじめに
血管肉腫は悪性度の高い血管内皮細胞の腫瘍である。この腫瘍は他の種に比較して犬で多く報告されており、 腫瘍と診断された犬の約2%を占める。どの臓器にも発生する可能性があるが犬では、脾臓原発の報告が一番多い。 他の原発部位は、右心房、皮膚、皮下組織、肝臓が挙げられ、まれに骨、中枢神経、腎臓、膀胱、筋肉、口腔内などに発生する。 今回、骨に発生した血管肉腫の症例に遭遇したのでその概要を報告する。
Ⅱ.症例
症例はシェットランドシープドッグ、8歳齢、体重13.15kg、去勢雄である。 他院より骨の悪性腫瘍が疑われるとのことで当院に紹介来院した。 レントゲン所見により右橈骨遠位で結節性の骨濃度の低下と骨増殖が認められたため、骨バイオプシーを実施した。
Ⅲ.経過
第3病日に実施した骨バイオプシーによる組織病理学検査の結果は骨の増生所見のみで炎症病変および腫瘍病変は認められなかった。 カルプロフェン、ミソプロストール、オルビフロキサシンを処方し、順調な経過であったが、第31病日目に再び跛行と疼痛を主訴に来院した。 カルプロフェンを増量したにもかかわらず跛行の程度はさらに進行し、第91病日には右前肢の腫脹が認められた。 細胞診を実施すると病変部から血様の液体が多量に抜去された。 右橈骨遠位部の骨増生に起因する動静脈断裂と診断し、圧迫包帯で止血した。 しかしその後も出血はおさまらず、腫瘍である可能性も考え、第120病日右前肢断脚術を実施した。 術前の血液検査ではPT時間が11.7秒と軽度に延長、フィブリノーゲンは50mg/dlと減少していた。 胸部レントゲン検査で肺への転移は認められなかった。摘出した右橈骨は結節状に著しく骨増生し骨髄腔は空洞化していた。 断脚後はアンピシリン、エンロフロキサシン、トラネキサム酸で治療して順調に経過し、術後3日目には凝固系検査も正常に回復した。 病理組織学検査の結果血管肉腫と診断されたため、 術後27日目よりアドリアマイシン30mg/m2を3週間おきに投与するプロトコールで抗がん剤治療を開始した。 術後148日を経過した現在肺への転移や抗がん剤による重篤な副作用もなく順調に経過している。
Ⅳ.考察
犬猫で骨に発生する腫瘍はほとんどが悪性腫瘍であり、良性腫瘍はまれである。 骨肉種は骨に最も多発する骨の原発性肉腫で、線維肉腫や血管肉腫はまれである。 犬の骨肉腫の予後は例外なく悪いが、血管肉腫は、悪性度は高いものの他の骨腫瘍の予後より悪くはない。 骨腫瘍は局所浸潤性のため、外科的治療には広範囲のマージンでの切除が必要となる。 今回のように一度の検査で腫瘍病変が発見されない場合もあるので、 腫瘍が疑われる症例では断脚術を含め外科的な治療を行うかどうかの見極めが重要である。
マーブル動物病院院長
難波 信一